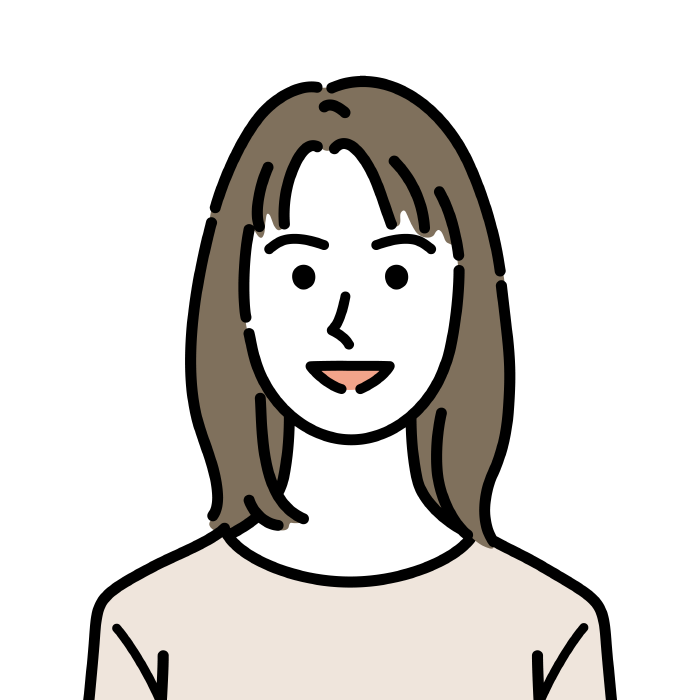- 設問1. 直近であなたが気になるプロダクト(化粧品以外でも可)を1つを取り上げ、それが人々に与える価値は何か、あなたなりの解釈を教えてください。(500字)
- 設問2. あなたが成長を感じたターニングポイントとその背景および取り組みについて、できるだけ具体的に教えてください。(500字)
- 設問3. (添削対象外)【動画提出】あなたにとっての「Beauty」の原体験と資生堂で成し遂げたいことについて詳しく教えてください。「Beauty」は美容に限らず、美意識や価値観など、あなたなりの解釈で構いません。(3分)
落ちる ES 例
直近で気になっているプロダクトは、サントリーの「あの夏休み自販機」である。これは、ある仕掛けを通して、誰もが一度は味わったような“懐かしい夏休み”を再体験できるというもので、飲料購入という日常的な行為の中に没入型のストーリーや演出が組み込まれている。自販機をきっかけに、まるで過去の記憶に入り込むような演出が始まり、童心に戻ったような感覚を味わうことができる。このイベントはキャンセル待ちが8000人と好評だ。このプロダクトは、飲料という身近なアイテムを通じて「懐かしさ」や「物語性」といった感情的価値を提供しており、親しみやすさと非日常性を両立させている点が印象的である。日常に埋もれていた記憶や感情を、商品の世界観とともに呼び起こす仕掛けに面白さを感じた。
はじめに、この設問に取り組む上で意識しておきたいポイントを紹介します。
まず、今回のような商品レコメンド型設問では、テーマから何が求められているかを正しく読み取る力が求められます。設問の本質は、「あなたが何に関心を持ち、それをどれだけ深く理解し、(募集職種である)ブランドマーケティングの業務とどう結びつけられるか」 にあることを理解しておきましょう。
資生堂のようなBtoCメーカーでは、「消費者ニーズをどれだけ理解しているか」も重視 されます。そのため、事前に次のような視点からリサーチしておくとよいでしょう。
・資生堂は、商品を通じて何を実現しようとしているのか
・各プロダクトに、どのような哲学が込められているのか
たとえば、資生堂採用ページ「メッセージ」には次のように語られています。
世界は変わり続ける。資生堂も変わり続けよう。私たちだけが生み出せる美しさを、この時代にふさわしく届けていこう。
ここにある、いくつもの舞台。そのすべてに、自分らしく挑む人がいる。ひたむきだからこそたどりつけた美学を、一人ひとりが持っている。いくつもの美学がひとつになって、人間の幸せに変わっていく。 資生堂はこれからも、そんな場所であり続けたいと思う。
あなたの美しい旅は、ここから始まります。
すべての仕事が、美しい。
Your Beautiful Journey Begins Here
引用元: メッセージ|AtFirst|SHISEIDO・RECRUTINGSITE
上記から、「美を通じて人々の幸せに貢献する、進化し続ける」というプロダクト哲学が資生堂の根底に息づいていることが読み取れます。時代の変化に呼応しながら、単なる機能性や流行にとらわれることなく、一人ひとりの「美学」に寄り添い、人の心に触れる“体験”としてのプロダクトを追求していると言えるでしょう。
これらを念頭に置き、次のような構成で回答を組み立てるとよいでしょう。
結論:どんなプロダクトか端的に紹介
前提:プロダクトの特徴と自身が気になる点
価値:プロダクトが人々に与える価値
では、ここから添削です。もとのES例は、「感じたこと」の描写が中心で、情緒的な価値の魅力を伝える文章としてはすぐれています。ただし、個人の感想に留まっており、ブランドマーケティング職に求められる“ニーズの構造理解”や“ターゲット分析”までは踏み込んでいない印象です。このままだと落ちる可能性があるため、私は次の3点を添削します。
受かる ES にするための添削ポイント
- 抽象だけでなく具体もあるか?
- ?を把握しているか?
- 業務への?があるか?
① 抽象だけでなく具体もあるか?
エピソードは、実際の行動や経験を具体的に伝えることで、読み手に納得感を与えることができます。
しかし、Beforeの「ある仕掛け」「没入型のストーリーや演出」「過去の記憶に入り込むような演出」といった表現は抽象的で、具体的な内容がイメージしにくくなっています。
一方、Afterでは「これは20年前の小学校の夏休みを体験できる体験型プロダクト」と、プロジェクトの概要を端的に示したうえで、体験の流れや仕掛けについても詳しく述べています。
直近で気になっているプロダクトは、サントリーの「あの夏休み自販機」である。これは、ある仕掛けを通して、誰もが一度は味わったような“懐かしい夏休み”を再体験できるというもので、飲料購入という日常的な行為の中に没入型のストーリーや演出が組み込まれている。自販機をきっかけに、まるで過去の記憶に入り込むような演出が始まり、童心に戻ったような感覚を味わうことができる
サントリーの「あの夏休み自販機」に興味を持った。これは20年前の小学校の夏休みを体験できる体験型プロダクトだ。とある自動販売機で特定の動作をすると、自販機の奥の家の玄関から突如カツヤという小学生の母親が登場。その家の中に招かれ、なっちゃんやC.C.レモンを振る舞われたり、謎解きをしたりすることができる。
このように、プロダクトの構造や演出を具体的に描くことで、読み手は実際に体験していなくても、内容を自然に思い浮かべることができます。
② ( ? )を把握しているか?
この設問では、「プロダクトが人々に与える価値は何か、あなたなりの解釈を教えてください」とあります。この点をふまえると、添削前の文章には価値に対する一定の洞察は見られるものの、やや一般的な印象です。